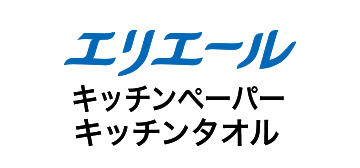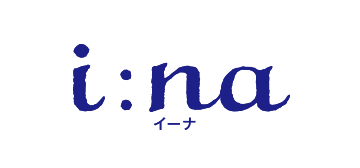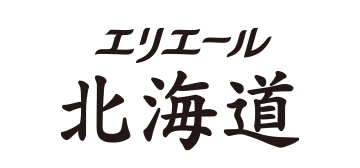おすわりは何ヵ月目から?始まる時期や練習の必要性などを解説
記事公開:2025.4.24
赤ちゃんの首がすわり、寝返りができたら、そろそろ「おすわり」のタイミングです。赤ちゃんの成長を楽しみにしているママやパパも多いのではないでしょうか。
この記事では、赤ちゃんのおすわりが始まる時期やサインのほか、おすわりとハイハイのタイミング、おすわりの注意点などについて紹介します。
赤ちゃんのおすわりは何ヵ月から始まる?
赤ちゃんのおすわりが始まる時期の目安は、生後6~8ヵ月頃です。この時期になると、おすわりに必要な筋肉や骨格が成長し、多くの赤ちゃんは大人の支えがあればおすわりできるようになります。
その後、背中を丸めて両手を床についた状態で少しのあいだおすわりができるようになる段階を経て、支えがなくても一人で座った状態をキープできる「ひとりすわり」ができるようになっていきます。ひとりすわりができたときが、「おすわりができた」という状態です。
こども家庭庁の「令和5年乳幼児身体発育調査」によると、ひとりすわりができるようになる時期は、生後5~6ヵ月未満で3.2%、生後6~7ヵ月未満で30.1%、生後7~8ヵ月未満で65.9%、生後8~9ヵ月未満で84.4%、生後9~10ヵ月未満で91.7%、生後10~11ヵ月未満で98.5%となっています。
このように、おすわりが完了する時期には個人差があるため、目安とされる時期にまだできていなくても、心配しすぎる必要はありません。ただし、生後11ヵ月を過ぎてもおすわりのサインが見られない場合は、医師や専門家に相談してみましょう。
赤ちゃんがおすわりを始めるサイン
赤ちゃんのおすわりは、まず上半身のバランスをとることから始まります。赤ちゃんがうつ伏せで腕を使って上半身を持ち上げたり、寝返りをしたりすることが増えてきたら、おすわりに向けた発達が進んでいる証拠です。
おすわりが始まる前のサインは、赤ちゃんを床に座らせたときに見られる、背中を丸めながら両手を前についてバランスをとる姿勢です。最初はすぐに前や横に倒れてしまう可能性があるので、大人は赤ちゃんから目を離さないようにしてください。赤ちゃんの腰のあたりを優しく支えてあげると安定しやすくなります。
両手を前についた状態でおすわりする姿勢に慣れてくると、そのままの姿勢をだんだんキープできるようになります。さらに安定すると、床に手をつかずにおすわりできるようになるでしょう。
おすわりの練習はしたほうが良い?

ママやパパの中には、なかなかおすわりしなくて心配な方や、早くおすわりできるようにサポートしてあげたいと考えるママやパパもいるでしょう。しかし、基本的に赤ちゃんには、無理な動きをさせてはいけません。ここでは、おすわりの練習の必要性や、遊びで取り入れる動きについてご紹介します。
赤ちゃんには無理におすわりの練習をさせる必要はない
おすわりの練習はしたほうが良いのか疑問に思う方もいるかもしれませんが、基本的には赤ちゃんに練習をさせる必要はありません。おすわりが完了する時期には個人差があるものの、赤ちゃんの筋力や運動能力が発達することで、自然とできるようになることが多いです。
普段の生活の中で、背中や首、おなか、腰などに必要な筋力がつき、おすわりのバランスがとれるようになっていきます。そのときまで焦らずに、ママやパパはゆっくり赤ちゃんの成長を見守ってあげましょう。
発達をサポートする動きを、遊びとして取り入れるのがおすすめ
おすわりを無理に練習する必要はありませんが、遊びの一環として、筋肉の発達をサポートする動きを取り入れてみるのはおすすめです。
赤ちゃんをうつ伏せにし、声をかけたり音を鳴らしたりして赤ちゃんが頭を持ち上げるのを促すと、背中や首の筋肉が強くなります。ずりばいや寝返りも全身の運動になるので、おもちゃなどを使って動作を促してあげてもいいでしょう。
また、ママやパパのひざの上に赤ちゃんを座らせて支えてあげながら、おすわりの姿勢に慣らしてあげるのも効果的です。
ただし、このような動きを取り入れる場合は、赤ちゃんの首がしっかりすわってから行うようにしてください。赤ちゃんの様子を見ながら、負担がかからないよう最初は短い時間から始めて、泣いたり、機嫌が悪くなったりするようであれば、別のタイミングで行うことが大切です。
おすわりとハイハイどっちが先?
おすわりとハイハイでは、一般的にはおすわりが先にできるようになります。おすわりができる子が増えるのは生後6~8ヵ月頃、ハイハイができるようになる子が増えるのは生後7~10ヵ月頃です。おすわりができるようになったら、もうじきハイハイをし始める時期ともいえるでしょう。
ただし、一般的におすわりやハイハイができるといわれる時期は、あくまで目安のため、個人差があります。おすわりからずりばい、その後ハイハイに移行する子がいれば、おすわりよりも先にずりばいを始める子もいます。
いずれの場合も、心配しすぎる必要はありません。それぞれの発達の目安とされる時期を参考に、焦らず見守ることが大切です。
赤ちゃんが実際におすわりを始めた時期についてママ・パパに調査!
おすわりができるようになると、赤ちゃんの視界が広がり、自分で姿勢を保つ時間も増えてきます。ママ・パパにとっても、成長を実感できる大切な瞬間ではないでしょうか。
そこで、クラブエリエール会員の先輩ママ・パパに、赤ちゃんのおすわりが始まった時期について調査しました。
【調査概要】
調査対象:未就学のお子さまがいるクラブエリエール会員の20~80代男女
調査期間:2025年2月3日~2月11日
調査手法:インターネットを利用したアンケート調査
有効回答数:1,062件
■お子さまは何ヵ月からおすわりを始めましたか?

赤ちゃんがおすわりを始めた時期を先輩ママ・パパに伺うと、最も多かった回答は生後6~7ヵ月未満で325人でした。次いで、生後7~8ヵ月未満が243人、生後8ヵ月以降が128人となっています。
おすわりが始まる時期には個人差がありますが、それぞれの赤ちゃんのペースで成長していくため、ゆっくりと見守っていくことが大切です。
赤ちゃんのおすわりの注意点
赤ちゃんが安定しておすわりできるようになるまでは、大人がそばで支えてあげることが大切です。続いては、赤ちゃんのおすわりの注意点について見ていきましょう。
無理におすわりさせない
まだ成長の準備段階にある赤ちゃんを、無理におすわりさせるのは避けてください。体に過度な負担がかかったり、姿勢が悪くなったりするおそれがあります。
また、おすわりが安定する前からベビーチェアに座らせるのも、赤ちゃんにとってはストレスになることがあります。体の成長をよく観察し、ゆったりとしたペースで準備が整うのを待ってあげましょう。
安全を確保して目を離さないようにする
赤ちゃんがおすわりに慣れていないうちは、安全を確保して目を離さないようにしましょう。おすわりを始めたばかりのときは、急にバランスを崩して倒れ、顔や頭をぶつけてしまうおそれもあります。床にやわらかいマットを敷いたり、家具の角をガードするカバーをつけたりして、赤ちゃんが過ごすスペースの安全を確保してください。
また、おすわりを始める時期の赤ちゃんは、手に取ったものを何でも口に入れてしまうことがあります。特におすわりが安定してくると、両手でいろいろなものをつかむようになります。
電池やたばこ、先のとがったもの、赤ちゃんの口に入る大きさのものなどは、手の届かない所に片付けてください。
監修者のご紹介
竹中 美恵子先生(小児科・内科・皮膚科・アレルギー科)
難病指定医、小児慢性特定疾患指定医、子どもの心相談医、高濃度ビタミンC点滴療法認定医、キレーション認定医。小児科医としての臨床を積みながら皮膚科や内科を学び、家族全員を1つの病院で診られるワンストップの病院を目指して姉妹で開業する。
女医によるファミリークリニック

【商品紹介】赤ちゃんのおしりをやさしく守る「グーン」シリーズ
おすわりをし始める時期の赤ちゃんは、動きが活発になりますが、肌はとてもデリケート。赤ちゃんの肌への刺激が少なく、漏れにくいおむつを選んであげたいものです。おしっこやうんちによるかぶれ、おむつの摩擦によるこすれなどに着目した「グーン」シリーズで、おすわり時期の赤ちゃんの肌をやさしく守ってあげましょう。
グーンプラス 敏感肌にやわらかタッチ Mサイズ

「グーンプラス 敏感肌にやわらかタッチ Mサイズ」は、赤ちゃんのおしりにやさしい「ぽこぽこクッションシート」を採用。ゆるうんちを広げずキャッチできるうえ、肌に触れる部分を最小限※に抑えました。肌に触れる表面シートには保湿成分を配合し、なめらかな肌ざわりで摩擦による肌への負担も軽減します。
※大王製紙ベビー用紙おむつ従来品との比較。
「グーンプラス 敏感肌にやわらかタッチ Mサイズ」については、下記のページをご覧ください。
グーンプラス 敏感肌にやわらかタッチ Mサイズ
グーンプラス やわらかタッチ パンツ Mサイズ

「グーンプラス やわらかタッチ パンツ Mサイズ」は、おなかまわりのふんわり感が約2倍※になった「ふわふわのびーるウエスト」を採用。おなかにゴム跡がつきにくく、のびのび動ける仕様です。肌に触れる表面シートには保湿成分を配合し、なめらかな肌ざわりでこすれによる肌への負担も軽減します。
※大王製紙ベビー用紙おむつ従来品との比較。
「グーンプラス やわらかタッチ パンツ Mサイズ」については、下記のページをご覧ください。
グーンプラス やわらかタッチ パンツ Mサイズ
グーン ぐんぐん吸収パンツ Mサイズ

「グーン ぐんぐん吸収パンツ Mサイズ」は、「スピード吸収体」が赤ちゃんのおしっこをたっぷり素早く吸収して、モレを防止してくれます。また、「全面通気性シート」がおむつ内の湿気を追い出して、いつでも肌がサラサラ。さらに消臭機能もついて、気になるニオイも軽減します。
「グーン ぐんぐん吸収パンツ Mサイズ」については、下記のページをご覧ください。
グーン ぐんぐん吸収パンツ Mサイズ
グーンプラス 汚れすっきりおしりふき

「グーンプラス 汚れすっきりおしりふき」は、赤ちゃんの繊細な肌を考え、厚手のシートに乳液成分を配合。肌にやさしいだけでなく、おしりにはりついてカピカピになったうんちも、浮かせてすっきり落とせます。
「グーンプラス 汚れすっきりおしりふき」については、下記のページをご覧ください。
グーンプラス 汚れすっきりおしりふき
赤ちゃんのおすわりは大人がサポートしながら見守ることが大切
赤ちゃんのおすわりは、目安として生後6~8ヵ月頃に始まるのが一般的とされています。ただし、発達には個人差があるため、おすわりの時期を気にしすぎる必要はありません。
成長とともに自然とできるようになるまで、普段の生活の中でママやパパがサポートしてあげながら、赤ちゃんのペースに合わせてゆっくり見守ってあげましょう。
よくあるご質問
おすわりが遅いと問題がある?
おすわりを始める時期の目安は、生後6~8ヵ月頃といわれています。ただし、発達の時期には個人差があり、あくまで目安のため、この時期より遅くても過度に心配する必要はありません。
なお、生後11ヵ月頃までにおすわりができない場合は、一度小児科で相談してみると安心です。
おすわりには練習が必要?
基本的に、おすわりのための特別な練習は必要ありません。おすわりに必要な筋肉は、うつ伏せやずりばい、寝返りなどの動作によって発達していきます。赤ちゃんとの遊びや日常の動きを通じて、自然な発達と成長をサポートしてあげましょう。
おすわりより先にハイハイがはじまっても平気?
おすわりより先にハイハイをし始めても、大きな問題はないでしょう。一般的には、ハイハイよりもおすわりが先にできることが多いですが、赤ちゃんによってはおすわりの前にずりばいを始める子や、おすわりとハイハイが同時に始まる子もいます。発達には個人差があるため、それぞれのペースで成長を見守ることが大切です。
画像提供/PIXTA
関連記事
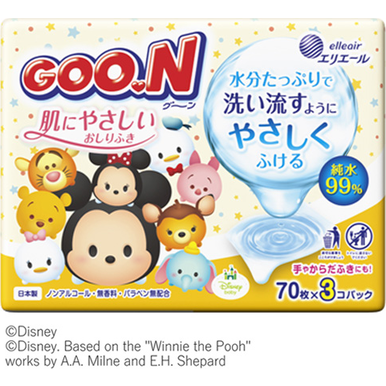



-
マカナロン
-
ひぃみ
-
-
freeze
-
-
-
-
-
-
-
-
-
めるもママ
-
-
-
-
ゎんゎん
-
-
onちゃん
-
小吉
-
かぐや姫
-
かりんとう
-
ぽっぽちゃんです。
-
こあらん
-
ヒライ
-
-
むぎちゃんパパ
-
-
-
ue
-
-
フランスパリ
-
こねこ
-
そうす
-
-
-
-
-
-
CHU☆
-
-
おじいちゃん犬
-
-
-
みいママ
-
-
ゴールデン珈琲
-
チェアー
-
-
-
-
Yoko Styles
-
-
はあと
-
シリカゲル
-
うさぎ♡
-
-
-
オレンジねこ
-
よ。
-
-
-
かわっち
-
-
-
-
-
-
フェンネル宜しくお願いします。
-
-
あさ
-
ひろきっち
-
みんみんタワー
-
-
占い好き
-
-
-
jun jun
-
ururusydtor
-
-
-
-
ドラミーゴ
-
ねこみみ
-
はるちゃん。
-
りりりりまる
-
-
あーあちゃん
-
-
とも☆
-
-
-
-
-
かぴまる
-
-
-
-
-
ゆゆゆん
-
なちゃぽ
-
sa-ya
-
六代目豆助よろしくお願いします。_(._.)_
-
omochi
-
ryoko
-
なんなん
-
よっしい
-
-
-
-
そうぱん
-
-
-
-
うさポンとうさピイうさぎのポンタとピイです、仲良く遊んでます。
-
ナギサ
-
くリぼう
-
sanri
-
-
-
-
-
-
0000
-
ゆきぽ
-
yyyyyy
-
さのさの
-
COCO助
-
テルチャン
-
-
-
しろぽん
-
まさきち
-
-
リー
-
あらふね
-
るるた
-
みるるん
-
あくびちゃん紙製品はエリエール一択!ふわふわ優しいものが好きです。
-
-
匿名希望
-
-
ちからこ
-
やもりお
-
-
-
-
あぶのニャンママ
-
風船
-
-
-
みみみーくん
-
-
-
happyくぅ
-
-
しばらん
-
ゆきべー
-
よう。
-
ミックスむっくん
-
新しい仔犬のしっぽ
-
JOY
-
うめっち
-
ゆんぽこ
-
北乃虎吉
-
草取り名人
-
-
-
-
代翁
-
リラックマルカ
-
-
yomogi
-
-
bluesky
-
雪ん子
-
暴走天使
-
-
ゆきあかり
-
まんまるスマイル
-
たー美よろしくお願いいたします。 エリエールいいですね!
-
-
フルーツ
-
ponta
-
なおちゃんこ
-
-
mimosa
-
-
-
ぴろこ
-
インコのママさん
-
-
ルッコちゃん
-
みゆあり
-
-
leeエコ
-
-
-
-
latte
-
ぽん
-
-
-
きたみん
-
nugisora
-
-
りえこ さく
-
-
白骨魚よろしくお願いいたします。
-
-
ミソサザイ
-
浜松のスナフキン
-
-
ぽんで
-
-
-
ショウタロウ
-
-
ぴーたろー
-
ディズニー大好き
-
うさうさぽん
-
-
ふーにゃ
-
KoooJ
-
-
シャギ
-
おたまご
-
-
あゆう
-
りょうさん
-
-
-
-
-
しろだいすき
-
-
けんたまま
-
オリ
-
モルモット
-
ゆきがえる
-
-
きいろ
-
シャンのおちり
-
かずさん
-
たけのこ舞茸
-
-
ヤムヤム
-
-
万三郎
-
なのはな
-
-
-
くいしんぼ
-